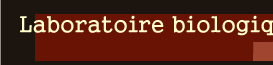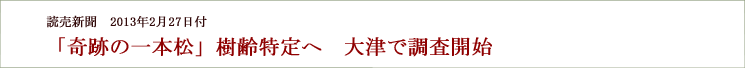
東日本大震災の津波に耐えながらも枯死した岩手県陸前高田市の「奇跡の一本松」の樹齢を特定する作業が26日、文化財の保存処理などを手掛ける民間会社「𠮷田生物研究所・文化財修復センター」(大津市)で始まった。
一本松はモニュメントとして現地で復元作業が進み、同研究所は幹表面の腐食を防ぐ処理を担当。樹齢は地元では「260年以上」と伝わるが、作業の一環として正確な測定を試みる。根元の近くから輪切りにした幹(直径約90センチ、厚さ最大約30センチ)を使い、年輪の状況や数などを調べる。伊東隆夫・京都大名誉教授(70)(木材組織学)の協力を得て分析し、結果は陸前高田市に報告する。
同研究所の𠮷田秀男社長は「どれだけ生きた松なのか、正確に知りたいと願う地元の人たちが多くいると聞いた。願いに応えたい」と話している。
一本松はモニュメントとして現地で復元作業が進み、同研究所は幹表面の腐食を防ぐ処理を担当。樹齢は地元では「260年以上」と伝わるが、作業の一環として正確な測定を試みる。根元の近くから輪切りにした幹(直径約90センチ、厚さ最大約30センチ)を使い、年輪の状況や数などを調べる。伊東隆夫・京都大名誉教授(70)(木材組織学)の協力を得て分析し、結果は陸前高田市に報告する。
同研究所の𠮷田秀男社長は「どれだけ生きた松なのか、正確に知りたいと願う地元の人たちが多くいると聞いた。願いに応えたい」と話している。

幹部分を使って始まった「奇跡の一本松」の樹齢を特定する作業(26日、大津市で)守谷由子撮影