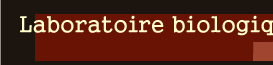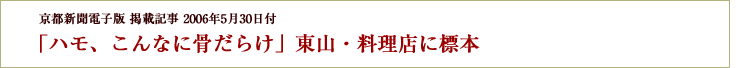
夏の味覚ハモのシーズンを前に、骨の多さがひと目で分かる骨格標本が京都市東山区の京料理店「馳走(ちそう)高月(こうげつ)」にお目見えした。「ハモを知り尽くしたい」という店主の朝尾朋樹さん(60)の10年越しの思いが実現した。前例のない標本は、料理人にはもちろん研究者らの注目も集めそうだ。
朝尾さんは1992年、骨切りをせず、1本ずつ骨を抜いて食感にこだわった調理法を考案。97年、著書「秘傳鱧(でんはも)料理」にまとめた。小骨は片身で約250本。身を傷つけず正確に抜くには標本が不可欠と考えた。2年前に知り合った𠮷田生物研究所(山科区)に依頼した。酵素で肉を溶かす工程に邪魔となる厚い皮を朝尾さんが自ら処理するなど、制作現場に通い詰めた。完成した標本は、体長約1・1メートルの魚の姿に精巧に復元したものと、歯やひれも含め約3500点を畳1枚ほどの額に展開した2種類。店内に飾れるよう変色を防ぐ処理を施している。

精巧に組み上げられたハモの骨格標本。肉食だけあって鋭い歯が並ぶ(京都市東山区)
朝尾さんは「ハモは京都料理の代表。徹底的に理解するのは、京都の料理人としての使命」とし、希望があれば誰にでも公開するという。
京都大総合博物館の中坊徹次館長はハモの骨格標本は初耳といい、「他の魚の標本と並べて構造比較する教材にしてみたい」と話している。
京都大総合博物館の中坊徹次館長はハモの骨格標本は初耳といい、「他の魚の標本と並べて構造比較する教材にしてみたい」と話している。