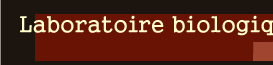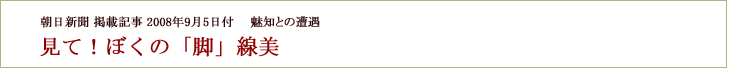
胸をはるように体を反らし、ひれを精いっぱい伸ばす姿。体長約30センチと大柄だが、生まれたばかりの「稚魚」だ。でも、鮮魚店で見慣れた魚とは何か違う。手足のように長く伸びたひれは、「肉鰭(にくき)類」と呼ばれる種類の特徴。そう、これは、世界でも珍しい「生きた化石」シーラカンスの稚魚の標本なのだ。
人間の遠い「ご先祖さま」になった魚が、初めて海から陸上に上がってきたのは4億年ほど前。シーラカンスと同じく肉鰭類の魚だった。シーラカンスは、このころからほとんど姿を変えていない。「生きた化石」と言われるゆえんだ。 標本のシーラカンスはアフリカ・タンザニア産。同国の国立水産学研究所と共同研究をしている東京工業大学の岡田典弘教授らの研究チームに贈られた、成魚2匹と稚魚、卵などのうちの一つだ。
その貴重な稚魚の標本化を、京都市山科区の𠮷田生物研究所が請け負った。同社は、遺跡の出土品や生物標本の保存処理を手がけている。生物の体内の水分を樹脂に置き換え、固めて標本化する技術では定評があり、東京・上野の国立科学博物館に展示されている魚やタコの標本も作製した。
シーラカンスは卵を体の外へ出さず、体の中でかえして産み落とす「卵胎生」の魚。このため、捕獲されたメスの体内から生まれる寸前の稚魚が見つかることがあるが、生きて泳いでいる稚魚を見たことのある人はいない。そこで、稚魚の生きた姿については想像も交えて標本化した。細部がよく見えるようにひれを大きく広げ、胸を張るように体を伸ばした。「大きく強い親のすぐ近くで、ちょっと威張って泳いでいるやんちゃな姿をイメージしました。標本作製にはドラマ性も求められるんです」と𠮷田秀男社長は話す。
稚魚を後ろで見守る成魚は、冷凍されて東工大に送られてきたシーラカンスをシリコンで型取りし、ポリエステル樹脂で作った複製。全長1.7メートルもある巨体は迫力満点だ。
成魚も稚魚も、茶色の体色にピンク色のまだら模様が印象的。これは捕獲されて届いた時の色で、生きているときにはもっと青っぽい色をしているのだそうだ。成魚のよろいのように厚く硬いうろこに比べて、稚魚のうろこは透明で、光が当たるとキラキラと輝いて見える。長く伸びた胸びれと腹びれは、どこか人間の手足を思い出させる。それもそのはず。この4本のひれが足へ進化し、背骨を持つ動物は陸へ進出したのだから。
シーラカンスは、人間の遠い祖先が海からやってきたことを我々に思い出させるためにやってきた、海からのメッセンジャーなのかもしれない。

小さなシーラカンスに新たな命が吹き込まれた。奥は成魚のレプリカ