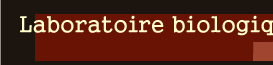2008.10.28(tue)

京都市伏見区東奉行町の財務省宿舎建設現場で、豊臣秀吉が建てた最初の伏見城の堀の遺構が見つかった。調査を委託された西近畿文化財調査研究所(兵庫県加東市)が27日発表した。堀の底から金箔(きんぱく)を張ったきせる、高麗青磁の茶托(ちゃたく)の破片も出土した。
伏見城は桃山―江戸時代に何度も建て替えられた。千田嘉博・奈良大准教授(中世考古学)は「当時の天下人の居城のうち、初代伏見城だけ実態が判明していなかった。中世から江戸時代の城の構造の変遷を知る手がかりになる」と話す。
発掘された堀は長さ11メートル、幅16メートル、深さ2.2メートル。南北方向に掘られ、西側護岸には4段の石垣が積まれていた。きせるは金箔が張られた銅製で、火皿と雁首(がんくび)(計6センチ)、吸い口(7センチ)の部分が見つかった。同研究所の村尾政人所長は「秀吉の黄金好みをまねて大名たちが使った品ではないか」とみる。高麗青磁は、秀吉の朝鮮出兵をきっかけに多く流入したとされる。
また、堀に隣接して江戸末期の伏見奉行所跡も見つかった。幕末の鳥羽伏見の戦いで新撰組(しんせんぐみ)など幕府軍が陣取り、薩摩軍の砲撃で全焼した史実通りに、焼けた瓦や土壁、崩れた石垣などが出土した。
〈伏見城〉 豊臣秀吉が1592年、伏見・指月(しげつ)に隠居所として初代の城を建設。1596年の地震で倒壊し、北約500メートルに移された。秀吉の死後に徳川家康が入城。1600年、関ケ原の戦いの前に石田三成らの軍によって落城したが、間もなく家康が再建。徳川家光が1623年に取り壊した。

金箔が張られたきせる=保存処理をしている𠮷田生物研究所提供